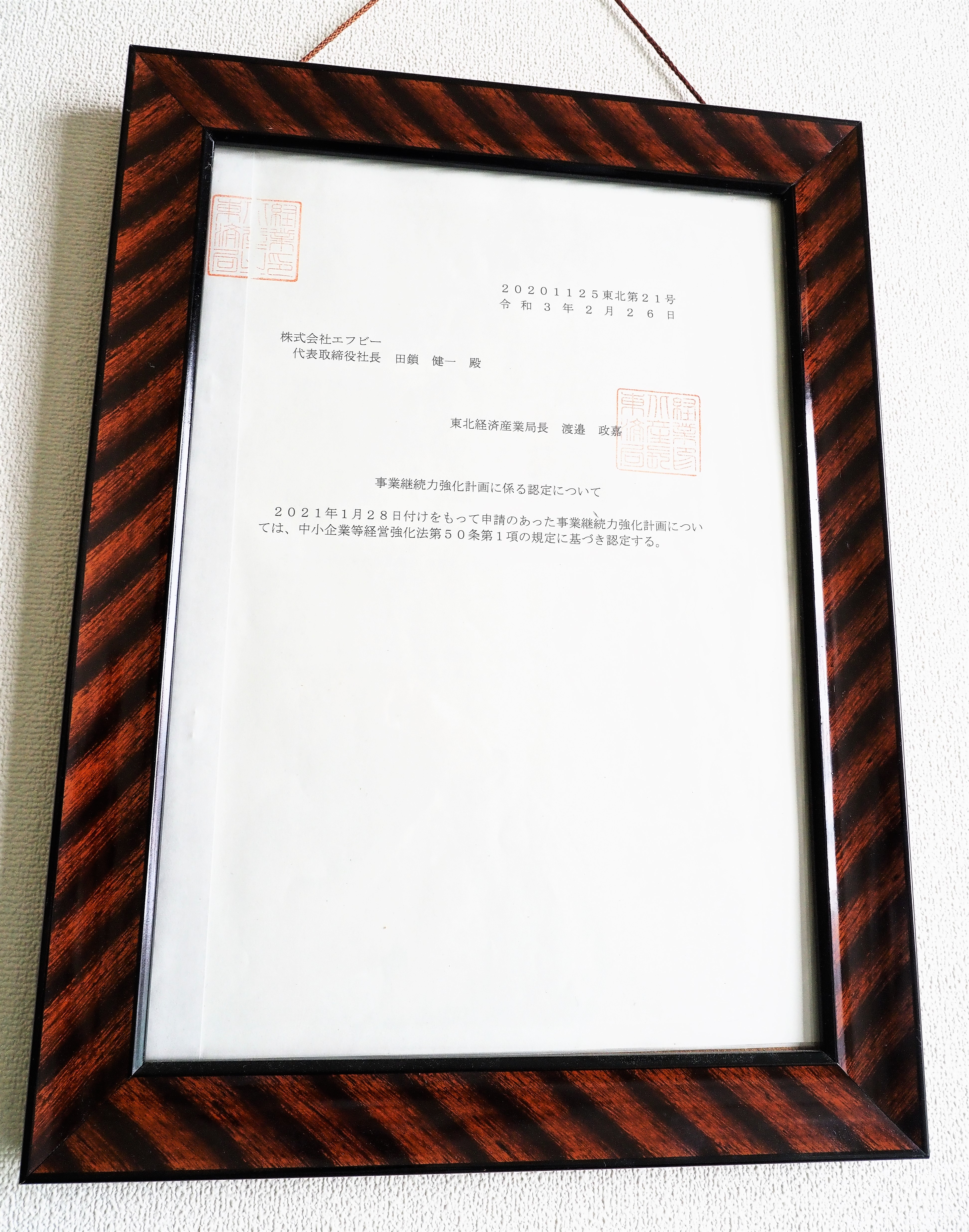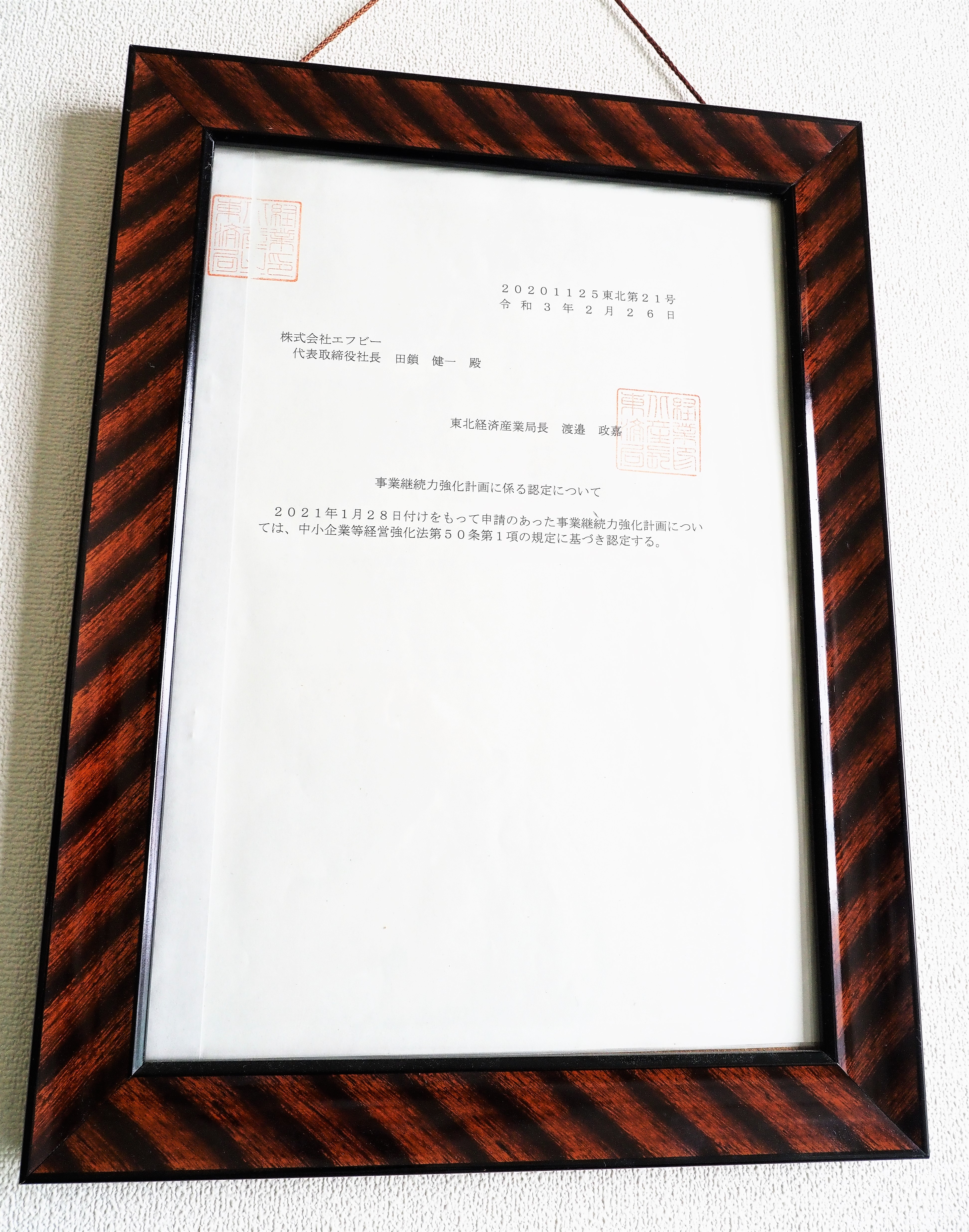いわて健康経営宣言事業所
 ● 健康診断の受診率85%以上を目指します
● 健康診断の受診率85%以上を目指します法令に従った定期健康診断を実施します。
● 健康サポート(特定保健指導)の実施率30%以上を目指しますメタボに着目した協会けんぽの特定保健指導を利用します。
● 検査・治療の推奨健診結果等で、再検査や治療の必要があった場合、医療機関を受診するように推奨します。
● スモールチェンジ活動の推奨日常的に従業員が気軽にできる健康づくりについて、事業所内に血圧計を設置します。
従業員の健康づくりを推進するため、これらの取組を積極的に実施していきます。
いわて健康経営事業所
1.定期健診受診率 実質 100 %
・労働安全衛生法の定期健康診断受診率100%、未受診者への受診勧奨の取組
2.受診勧奨の取組
・再検査、精密検査等が必要とされた従業員への受診を促すための取組又は制度
3.食生活の改善、運動機会の増進などに向けた取組
・健康課題を把握し、食生活改善や運動機会の増進などの継続的な取組
・社内健康イベントの開催又は社外健康イベントへの組織としての参加
4.受動喫煙対策に関する取り組み
・健康増進法に基づく必要な措置(敷地内禁煙、建物内禁煙又は完全分煙)
5.健康情報の定期提供
・健康をテーマとした研修会の実施又は社外研修等への参加、月1回の全従業員への健康情報の提供
これらの取組を強化し、従業員の健康づくりを推進していきます。